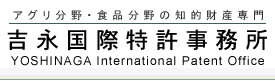|
| Q1.「知的財産権」とは何か? | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そもそも「知的財産権」って何のことでしょうか?実際に「知的財産権」という権利があるのでしょうか?答えは「NO」です。
|
| Q2. なぜ特許を取得する必要があるのか? |
|---|
「新たに開発した技術を広く普及させるには、特許を取得しないほうがよいのでは?」。このような質問を受けることがあります。特許権は独占権であり、権利を有していない者は自由に実施できないからです。しかし、「特許を取得する=普及しない」という構図は必ずしも真実ではありません。 一方、特許を取得していた場合はどうでしょうか? このように、特許は「自社の技術を守る」という側面と、「財産として活用する」という2つの側面があります。いずれの側面においても、特許によって開発者に利益を得る機会を与え、その利益を新しい技術の開発に投入することによって、また優れた技術を創造することができるのです。これが「知的創造サイクル」と呼ばれているものです。 |
| Q3. 「特許」と「特許権」って違うの? | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知的財産に関する用語は難解なものが多いですね。本書ではなるべく法律用語の使用を避けますが、基本的な用語は押さえておきたいものです。
|
| Q4.どんな発明が特許されるのか?(その1) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「特許」などと聞くと、さも優れた大発明でなければ認められないと思い込んでいる方が多いような気がします。しかし実際には「えっ?これも特許なの?」というものもあるのです。 (1)特許法上の発明であること
|
| Q5.どんな発明が特許されるのか?(その2) |
|---|
一般に企業で開発されたような技術は先ほど説明した「特許法上の発明」の要件及び「産業上利用できる発明」の要件は満たしていることがほとんどでしょう。いってみれば(その1)で説明したことは特許の前提となる要件です。特許庁の審査でしばしば問題となるのがこれから説明する要件です。 (3)新しいこと(新規性) (4)容易に考え出すことができないこと(進歩性) |
| Q6.どんな発明が特許されるのか?(その3) |
|---|
(5)先に出願されていないこと (6)公序良俗に反しないこと (7)明細書の記載要件を満たすこと (8)発明の単一性を満たすこと |
| Q7.発明の種類(カテゴリー)とは? |
|---|
発明には大きく分けて「物の発明」と「方法の発明」があります。「方法の発明」はさらに「単純方法の発明」と「生産方法の発明」に分けられます。発明のカテゴリーによって範囲権利が異なるので、ぜひ押さえておきたいところです。 (1)物の発明 (2)方法の発明(単純方法の発明)
発明のカテゴリーが何に該当するか、実は簡単に判別できる方法があります。それは、【特許請求の範囲】の請求項の語尾を見るのです。 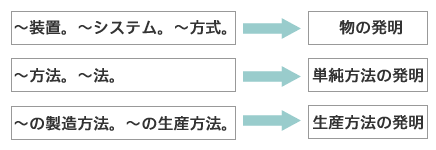 |
| Q8.特許出願を依頼する際に必要な資料は? |
|---|
実は、特許出願は個人で行うもできます。 そこで特許出願の専門家である弁理士が代理人となって特許出願を行うのです。では弁理士に特許出願を依頼する際、どんな資料があればよいのでしょうか?中には特許公報の項目に基づいて、出願書類の形でドラフトを提出してくださる優秀な方もいますが、すべてのクライアントにそこまでは要求できませんので、一般的に弁理士が知りたい情報を以下に列挙します。
|
| Q9.出願から登録までの手続は? |
|---|
(1)特許出願 (2)出願公開 (3)出願審査の請求 (4)審査 (5)登録・権利発生 (6)権利の消滅 |
| Q10.「PAT.P」って何のこと? |
|---|
特許法では、特許に係る商品に対して特許表示を奨励しています。これは、特許表示によって第三者がその商品に関する技術に特許権が発生していることを理解し、特許権の侵害を未然に防ぐ意味もあります。また、特許出願中においてもその旨の表示はできます。例えば、「PAT.P」(パテント・ペンディング)という表示や「特許出願中」という表示を見たことはありませんか? これはどちらも同じ意味で、まだ特許にはなっていないけれど特許出願はしている、ということを意味するものです。但し、日本では法律上の特許表示には当たりません。 (1) 安易な模倣の防止 (2) 付加価値の付与 |
| Q11.本当に特許出願してもよいですか? |
|---|
特許出願をする以前に、それが本当に特許出願してよい発明か否か、必ず検討しておかなければならないことがあります。 それは特許出願しようとしている対象がノウハウである場合です。 ノウハウとは、秘密にしている限り他人には知り得ない技術情報です。出願すべき対象がノウハウである場合、特許になれば問題ありませんが、特許にならなかった場合は問題です。
|
| Q12.「特許は儲かる」は本当? |
|---|
昔ほどではありませんが、世間では「特許は儲かる」という風潮がいまだに存在しているように思います。
|
| Q13.侵害を発見したらどうすればよいか? |
|---|
第三者が他人の特許発明を無断で実施することは特許権の侵害になります。その中には意図する侵害もあれば、意図しない侵害もあるかもしれません。しかし、いずれにしてもそのままの状態を放置すれば、特許権者の利益は損なわれることになります。そのため、特許権者は特許権に基づいて、差し止め請求、損害賠償請求などの対策を講じるべきです。 (1) 特許の有効性を確認する (2) 侵害行為を特定する (3) 警告書を作成する |
| Q14.警告書が届いたらどうすればよいか? |
|---|
自社製品の販売が好調に推移していた矢先、ライバル会社から突然、特許権侵害の警告書が内容証明郵便で届きました。さあ、どうすればよいでしょうか? (1) 警告書の内容を検討する (2) 事実の確認をする |